カブトムシを飼育していると、「カブトムシ 成虫になったら何をすればいいの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
卵から成虫までの過程には多くの手間がかかり、特に成虫になってからの管理は育て方のポイントが変わってきます。実際、成虫になる確率は環境によって大きく左右されるため、正しい知識が必要です。
成虫期にはマットの交換頻度や湿度の管理、ストレスを与えない飼い方に注意しなければなりません。マット選びひとつでもカブトムシの寿命に影響するため、成虫におすすめのマットを知ることも重要です。
さらに、卵を見つけたらどう対応すべきか、幼虫の共食いをどう防ぐかといった知識も欠かせません。
この記事では、カブトムシが成虫になった後の育て方や注意点を中心に、飼育初心者でも安心して実践できる情報をわかりやすくまとめています。
- 成虫になった後の飼い方
- マット交換の必要性と頻度
- 成虫の寿命と管理方法
- 幼虫から成虫までの流れ
この記事を書いてる人
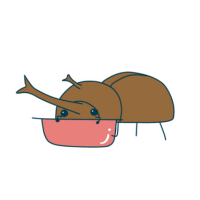
ナツ
- どんな人?
30代フリーランサーで二児の父してます。 - ブリード歴は?
2022年春よりカブトムシ・クワガタのブリード開始。 - どんな種類を飼育してる?
カブトムシはヘラクレスやサタンなど、クワガタはニジイロやメタリフェルなどを主にブリードしており、常時200匹以上飼育中!
カブトムシが成虫になったら何をする?

- カブトムシが成虫になる確率とは
- 成虫の飼い方と注意点について
- 成虫になったらマットは交換する?
- 成虫の寿命はどれくらい?
- 成虫育成におすすめのマット
カブトムシが成虫になる確率とは
カブトムシが卵から成虫になるまでには、いくつかの段階があり、そのすべてを問題なく通過できる個体は意外と限られています。自然下での生存率は決して高くなく、全体のおよそ30~50%程度と考えられています。
このような数字になる理由は、外的な要因と飼育環境の影響が大きいからです。例えば、幼虫の時期に温度管理が不十分であったり、通気性の悪いマットを使用していた場合、酸欠や腐敗によるダメージで命を落とすことがあります。
 ナツ
ナツ筆者の飼育環境では国産のカブトムシの幼虫は、今のところ共食いを起こしたことはありません!
一方、室内でしっかりと管理された飼育環境下では、成虫になる確率は70%以上に高まることもあります。これを可能にするには、湿度管理・マット交換・栄養補給などを丁寧に行う必要があります。
つまり、適切な飼育を行えば高確率で成虫に育てることはできますが、自然の中では多くのリスクが潜んでいるため、生き残る個体は限られるというのが実情です。
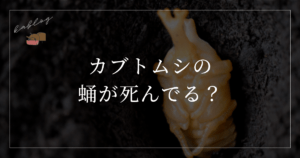
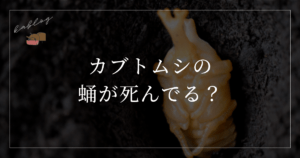
成虫の飼い方と注意点について


カブトムシが成虫になったあとの飼育では、幼虫期とは異なるポイントに注意する必要があります。
まず飼育容器は、風通しのよいものを選び、1匹ずつの飼育をおすすめします。複数を同じ容器で飼うと、エサの奪い合いや喧嘩が起こることがあるからです。容器の底には昆虫専用のマットを敷き、乾燥しすぎないように定期的に霧吹きで湿らせます。
エサには昆虫ゼリーが便利で、栄養バランスも整っているため、毎日新しいものに交換するのが理想です。ただし、人が食べる果物を与える際には、腐敗しやすい点に注意が必要です。
また、直射日光が当たる場所やエアコンの風が直接当たる場所では、体調を崩しやすくなるため避けてください。音や振動もストレスの原因になることがあります。
このように、成虫の飼育には「清潔な環境」「ストレスを与えない工夫」「適切な温湿度管理」が欠かせません。ちょっとした変化が命に関わることもあるため、日々の観察が大切です。
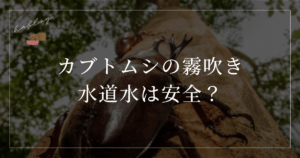
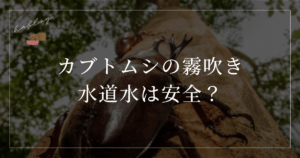
成虫になったらマットは交換する?


成虫になったカブトムシにも、マットの管理は欠かせません。
多くの人が「幼虫のように土に潜らないから、マットは不要では?」と考えがちですが、実際には違います。成虫も日中はマットの中で静かに過ごすことが多く、その環境が悪化すると体調に影響を及ぼします。
マットは単に敷くだけのものではなく、湿度の維持や休息スペースとして重要な役割を果たしています。
また、エサのゼリーがこぼれたり排泄物がたまったりすると、マットはすぐに不衛生になります。これを放置すると、カビやコバエが発生し、カブトムシにストレスや病気のリスクを与えることになります。
マットの交換頻度としては、1~2週間に一度のペースが適切です。
使用状況や容器の広さによっては、それよりも早めの交換が求められる場合もあります。なお、全部を一度に入れ替えると環境が急変してカブトムシが驚いてしまうことがあるため、汚れている部分だけを取り除いて、新しいマットを少しずつ加える方法が安全です。
このように、成虫期でもマットの管理はカブトムシの健康に直結します。放置せず、定期的なチェックとメンテナンスを心がけることが、長く元気に飼育するためのコツです。
成虫の寿命はどれくらい?
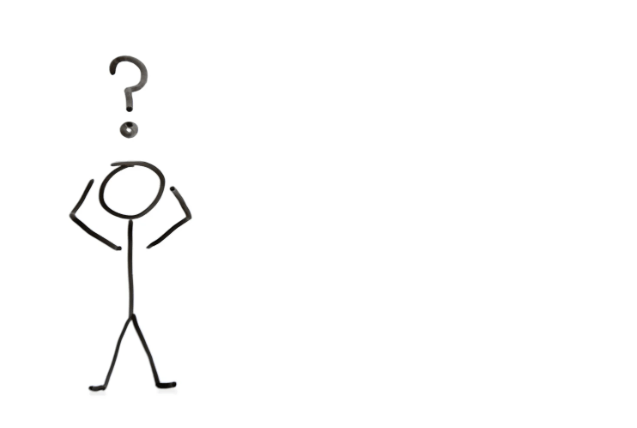
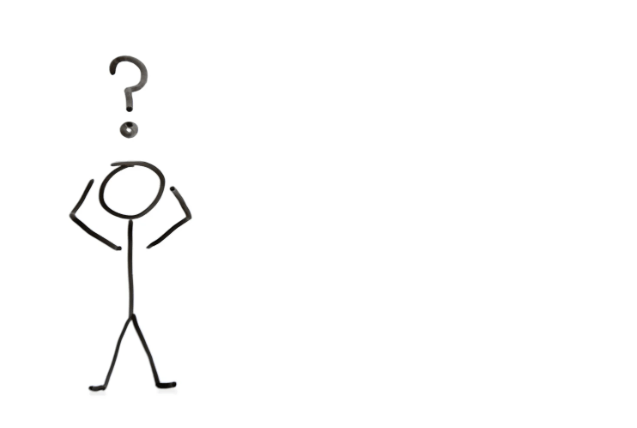
カブトムシの成虫としての寿命は、一般的に1~3ヶ月程度です。
梅雨明けから夏の終わりにかけて活動する姿が見られるのは、この短い寿命によるものです。人によっては、飼育を始めたばかりなのにすぐに動かなくなった、という経験をすることもあるでしょう。
この短命さには、生態的な理由があります。カブトムシは幼虫期間に長い時間をかけて栄養を蓄え、成虫になると一気にエネルギーを使って繁殖活動を行います。



成虫期は「種を残すための期間」として設計されているのです!
一方で、飼育環境が適切であれば、寿命を最大限まで延ばすことは可能です。例えば、直射日光や高温を避けた室内で管理し、湿度を保ち、毎日清潔なゼリーを与えると、3ヶ月以上生きる個体もいます。気温は22〜28℃程度が適しており、急な温度変化は避けた方が良いでしょう。
寿命が近づくと、動きが鈍くなり、エサの消費量も減少します。この変化を見逃さず、落ち着いた環境で見守ることが大切です。無理に動かしたり、新しい環境に移したりすると、余計にストレスを与えてしまう可能性があります。
つまり、成虫の寿命は本来短いものの、飼い主の工夫次第で充実した期間を過ごさせることはできます。毎日の観察と配慮が、その短い命を支える鍵になります。
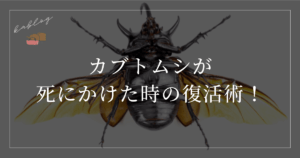
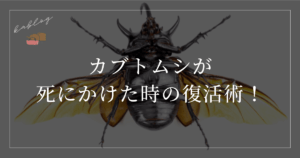
成虫育成におすすめのマット


カブトムシの成虫を快適に育てるためには、適切なマットの選定が欠かせません。マットは単なる床材ではなく、湿度の保持や衝撃の吸収、日中の隠れ場所として重要な役割を果たします。成虫が健康に過ごすには、清潔かつ適度な水分を含んだマットを用意することが基本となります。



成虫に適している管理用のマットはいろんな種類がありますが、針葉樹の床材がおすすめです。
針葉樹が原料の成虫管理用マットは、コバエが湧かないのが最大のメリットになります。
産卵をさせたい場合には、発酵マット(広葉樹)を選びましょう!
市販されている成虫用マットには、脱臭効果や防虫加工が施されているタイプもあります。こうした機能付きマットは、室内での飼育にも安心感を与えてくれるでしょう。
選ぶ際には、パッケージの記載やレビューも参考になりますが、実際に使ってみて湿度やニオイの変化を観察することも大切です。最終的には、カブトムシの様子を見ながら最適な環境を整えていくことが、快適な飼育につながります。
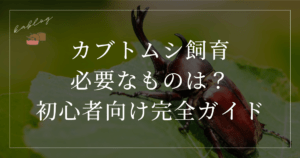
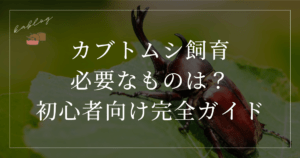
カブトムシに成虫になったら準備したいこと


- 成虫の育て方と基本のポイント
- 幼虫の共食いを防ぐ対策
- 卵から成虫までの成長過程
- 卵を見つけたらどうする?
- マット交換の頻度とタイミング
- 成虫の飼育に必要な環境づくり
成虫の育て方と基本のポイント
カブトムシの成虫を元気に育てるためには、いくつかの基本的なポイントを押さえておく必要があります。野生の個体とは異なり、飼育環境下では人の手が環境のすべてを左右するため、飼い主の知識と管理がとても重要です。
まず温度管理ですが、カブトムシは22〜28℃前後の気温を好みます。
高温すぎると弱ってしまい、逆に20℃を下回ると活動が鈍くなります。直射日光を避け、風通しの良い場所で飼育しましょう。湿度もある程度必要で、マットが乾燥しすぎないよう霧吹きで調整すると効果的です。
次に、エサの管理も重要です。
カブトムシ用の昆虫ゼリーを使うのが一般的で、糖分と水分を効率よく補給できます。果物を与える人もいますが、腐敗しやすくコバエの原因になりやすいので、ゼリーの方が無難です。
容器は最低でも成虫が羽を広げられる程度の広さが必要です。フタには通気口があり、脱走防止のためしっかり閉まるものを選びましょう。夜間によく活動するため、昼間は静かな場所で休ませてあげるのが理想的です。
これらの管理を丁寧に行えば、成虫はストレスなく快適に過ごせます。小さな変化に気づく観察力も、育成において大切なスキルの一つです。
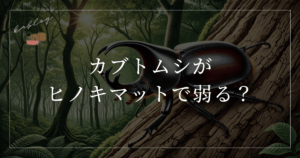
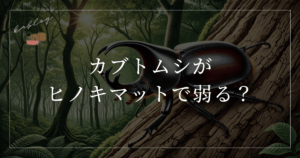
幼虫の共食いを防ぐ対策
カブトムシの幼虫を複数一緒に育てていると、稀に共食いが起こることがあります。自然界ではあまり見られない現象ですが、飼育環境下ではスペースや栄養が不足した場合に発生することがあるため、対策が求められます。
共食いの最大の原因は「ストレス」と「栄養不足」です。密閉された容器の中で、十分なエサや空間がないと、幼虫同士が刺激し合い、攻撃的な行動に出ることがあります。これを避けるには、なるべく一つの容器に1匹ずつ分けて飼育するのが理想です。
マットの質にも注意が必要です。栄養価が低いものを使用すると、幼虫がエサを求めて動き回り、他の個体に接触する機会が増えます。発酵マットや栄養添加されたマットを使うことで、エサ不足を予防することができます。
さらに、マットが汚れてアンモニア臭が強くなると、幼虫にとって過酷な環境になります。これも攻撃性を高める原因となるため、定期的にマットの状態を確認し、必要に応じて交換することが大切です。
このように、共食いの防止には、十分なスペース、栄養の確保、環境の清潔さという3つのポイントを意識することが必要です。丁寧な管理が、健康な成長につながります。



とはいえ、国産のカブトムシの場合は、よっぽどのことがない限り共食いはしないです!
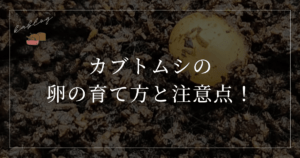
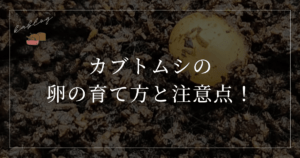
卵から成虫までの成長過程
カブトムシは卵から始まり、成虫になるまでにいくつかの段階を経て成長します。それぞれの時期に適切な管理を行うことで、元気な成虫を育てることができます。
最初のステージは「卵」です。
産卵後、白くて小さな卵がマットの中に産み付けられます。この段階では刺激を与えず、静かな環境で孵化を待つことが大切です。おおよそ2〜4週間で孵化し、幼虫になります。
次の「幼虫期」は最も長く、通常は5〜9ヶ月ほど続きます。
この期間中はマットの中で栄養を取りながら大きくなり、3回の脱皮を経て終齢幼虫へと成長します。幼虫は光を嫌い、外に出てくることはほとんどありません。成長の様子は体重や体の大きさで確認することができます。
十分に成長すると、幼虫は「蛹室(ようしつ)」という自分の部屋をマット内につくり、そこで「蛹(さなぎ)」になります。この蛹期は約1ヶ月程度で、動かずにじっと変態の準備をしています。
この期間中に容器を振動させたりマットを掘り返したりすると、正常な羽化が妨げられる可能性があるため、注意が必要です。
蛹から脱皮して羽が固まれば、ようやく「成虫」として姿を現します。ただし、羽化直後の成虫は体が柔らかくデリケートです。1週間ほどはそっとしておき、十分に体が固まってからエサや環境を整えると良いでしょう。
このように、卵から成虫までの成長には数ヶ月以上かかりますが、それぞれの段階を理解し適切に対応することで、無事に成虫へと導くことができます。飼育の醍醐味でもあるこの成長過程を、丁寧に観察しながら楽しむことが大切です。
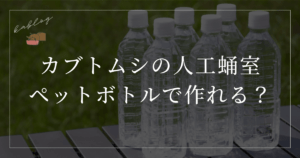
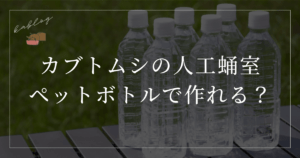
卵を見つけたらどうする?


カブトムシの飼育中に卵を見つけたら、慎重な対応が求められます。見つけた直後の行動によって、その後の孵化や幼虫の成長に大きく影響するからです。
まず、卵の扱いには注意が必要です。
カブトムシの卵は非常に小さく、柔らかく壊れやすい状態です。そのため、手で直接つまんだり、マットを大きくかき回したりすると、潰れてしまうおそれがあります。



スプーンや専用のピンセットなどでやさしくすくい上げるように移動させると安全ですよ!
次に、卵の保管場所についてです。見つけた卵は、別の容器に新しいマットを敷いて移し替えることが望ましいでしょう。このとき使用するマットは、柔らかくて湿度を適度に保てる発酵マットが理想的です。卵の周囲には、親が産みつけた時と同じような環境を再現するために、少量の元のマットも一緒に移すと良い結果が得られやすくなります。
さらに、容器は直射日光を避けた安定した温度の場所に置き、静かな状態を保つことが大切です。卵は約2〜4週間ほどで孵化することが多いため、その間は過度な振動や環境変化を避けましょう。
このように、卵を見つけた際には過度に触らず、慎重に扱いながら適切な環境に移し替えることが、健康な幼虫を育てる第一歩になります。
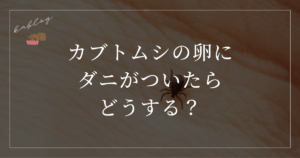
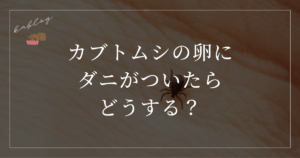
マット交換の頻度とタイミング


カブトムシの成虫を快適に飼育するには、マットの交換頻度とタイミングを正しく理解しておく必要があります。マットが汚れた状態のままだと、悪臭やカビの原因となり、成虫の健康にも悪影響を及ぼします。
交換の目安としては、およそ1〜2週間に1度が理想的です。
ただし、これはマットの種類や飼育している数、エサの種類などによって前後します。例えば、昆虫ゼリーを与えている場合は液だれしやすく、マットが早く傷むため、より短い間隔での交換が必要になることもあります。
タイミングを見極める方法としては、マットの色や臭いの変化に注目すると良いでしょう。
黒ずんで湿り気が強くなってきたり、アンモニア臭が漂うようであれば、早めに交換することをおすすめします。成虫がよく動き回ったり、マットの中に潜ったりする様子が少なくなってきた場合も、環境が悪化している可能性があります。
マット交換は、ただの掃除ではなく、カブトムシが健康に過ごすための大切なメンテナンスです。目安にとらわれすぎず、日々の観察をもとに最適なタイミングで行うことが長生きにつながります。
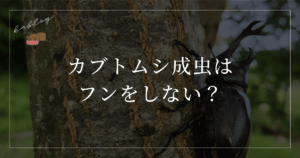
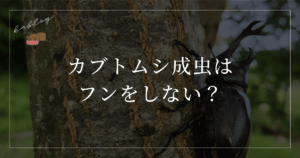
成虫の飼育に必要な環境づくり
カブトムシの成虫を健康に育てるためには、環境づくりが非常に重要です。
自然とは異なり、飼育ケースの中では飼い主がすべての環境要素をコントロールする必要があるため、快適な空間を整えることが欠かせません。
まず最初に考えるべきは温度管理です。
カブトムシの成虫は、25℃前後の温暖な環境を好みます。高すぎると体力を消耗し、低すぎると動きが鈍くなるため、極端な温度変化は避けましょう。
湿度も成虫の体調を左右します。マットが乾燥していると、カブトムシが脱水状態になることがあります。そのため、マットには適度な湿り気を保たせ、乾燥が気になる場合は霧吹きで調整すると安心です。
容器の選び方も重要です。成虫は夜行性でよく動き回るため、十分な広さがあるケースが理想です。目安としては、1匹あたり15cm×15cm以上のスペースを確保すると動きやすくなります。フタには通気孔があり、脱走防止のロック機能があると安全です。
内部には、登り木や隠れ家になる樹皮などを設置してあげましょう。これによりストレスを軽減し、自然に近い動きができるようになります。エサは昆虫ゼリーを中心に与え、こぼれにくい餌皿を使うと清潔な状態を保ちやすくなります。
このように、成虫の飼育には「温度・湿度・広さ・レイアウト」の4つが基本となります。日々の観察を通して、カブトムシが落ち着いて過ごせる空間を整えてあげることが長く飼育を楽しむためのコツです。
まとめ|カブトムシが成虫になったら知っておきたい15の基本ポイント
この記事のポイントをまとめます。
- 成虫になる確率は自然下で約30〜50%と低い
- 室内飼育なら成虫になる確率は70%以上まで上げられる
- 成虫にはストレスの少ない静かな環境が必要
- 飼育容器は1匹ずつの飼育が望ましい
- 成虫も日中はマットに潜るためマットは必須
- マットの交換は1〜2週間に一度が適切
- マットが汚れた部分のみを部分的に交換するのが安全
- 寿命は通常1〜3ヶ月程度と短い
- 気温22〜28℃、湿度の維持が成虫飼育には重要
- 昆虫ゼリーは毎日新しいものに交換するのが理想
- エサの液だれはマット劣化の原因になる
- 成虫育成には防虫加工や脱臭効果付きマットが使いやすい
- 幼虫の共食い防止には個別飼育と栄養管理が必要
- 卵を見つけたら別容器にやさしく移動させる
- 成虫飼育には登り木や隠れ家の設置でストレス軽減が図れる

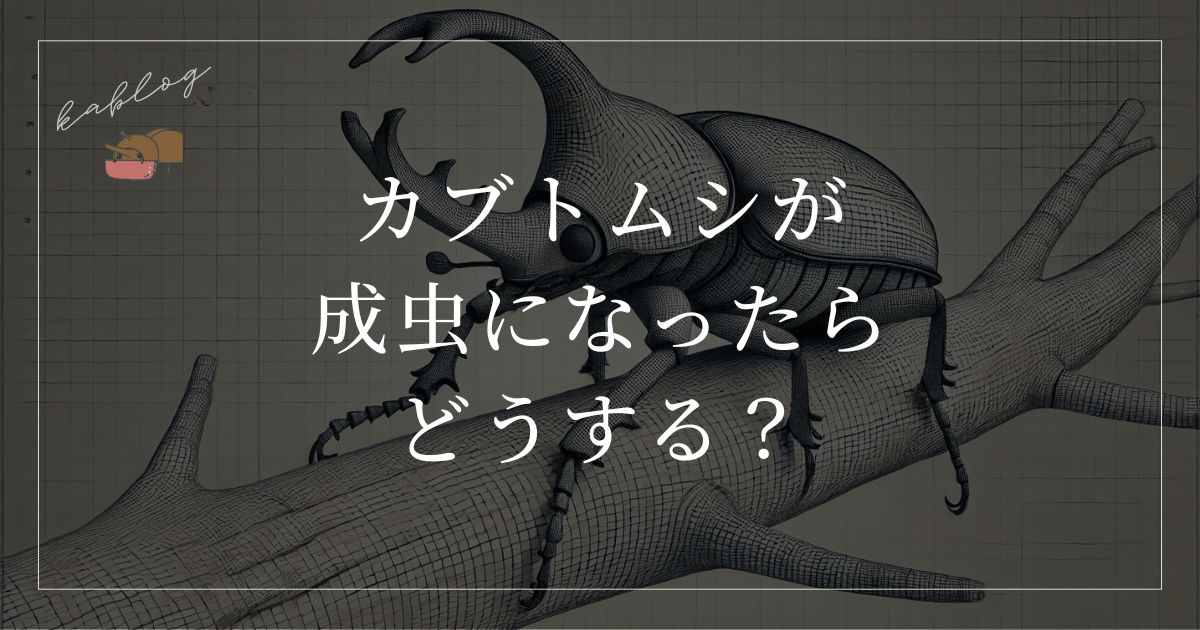
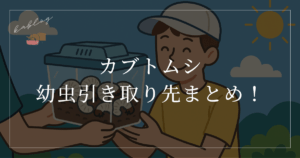
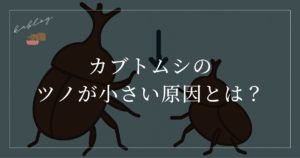
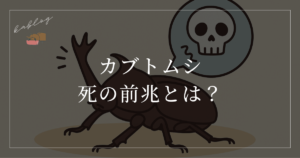
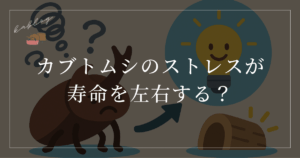
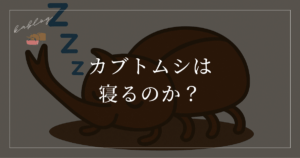
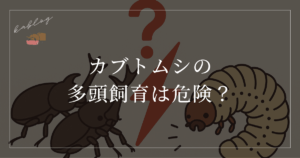
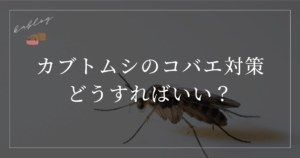
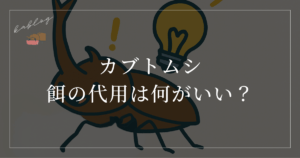
コメント