カブトムシを飼育していると、「これで合っているのだろうか」と不安になる瞬間があるかもしれません。
特に、普段と違う動きを見せたり、元気がなくなったりすると、ストレスの影響を疑いたくなるものです。
カブトムシは環境の変化に敏感で、ちょっとした振動や明るさ、虫かごの狭さなども負担になることがあります。夜にうるさく動き回るのも習性だけではなく、落ち着かない環境が原因のこともあるのです。
さらに、適切でない飼い方や床材の代用にキッチンペーパーを使うことが、知らず知らずのうちに寿命を縮めてしまうこともあります。また、死の前兆や体がバラバラになってしまう理由についても、正しい知識がないと驚いてしまうでしょう。
この記事では、快適な飼育環境の整え方や虫かごの選び方、注意点などを丁寧に解説していきます。
- ストレスの原因と対策
- 飼育環境の整え方
- 寿命への影響
- 異常行動の見分け方
この記事を書いてる人
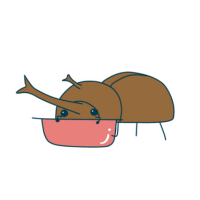
ナツ
- どんな人?
30代フリーランサーで二児の父してます。 - ブリード歴は?
2022年春よりカブトムシ・クワガタのブリード開始。 - どんな種類を飼育してる?
カブトムシはヘラクレスやサタンなど、クワガタはニジイロやメタリフェルなどを主にブリードしており、常時200匹以上飼育中!
カブトムシにストレスを与える原因とは
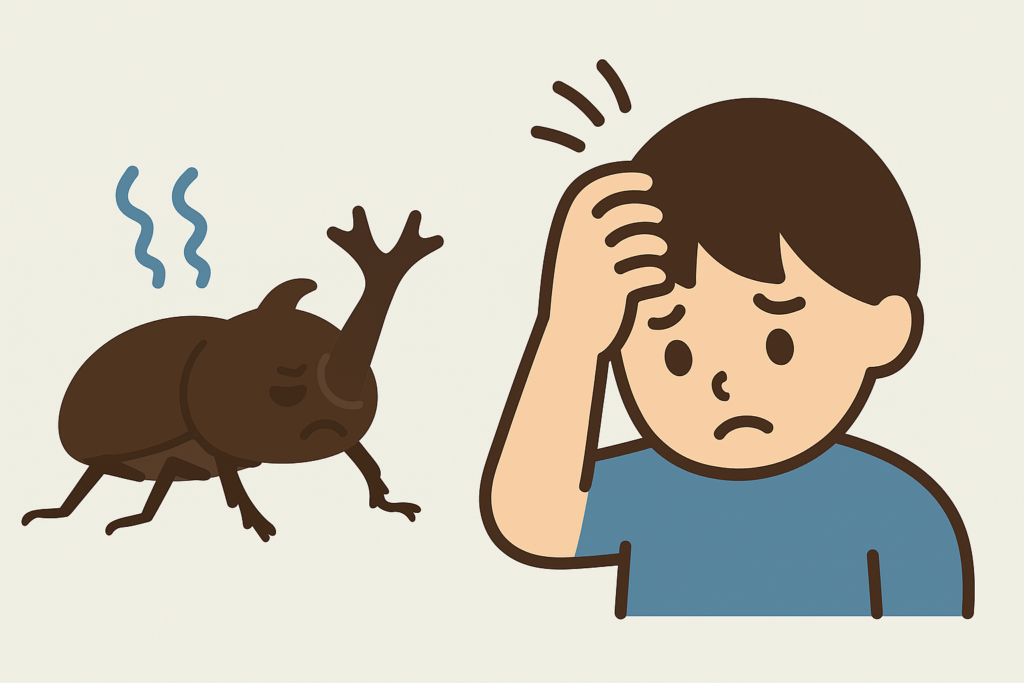
- ストレスが寿命に与える影響
- 夜にうるさいのはストレスのせい?
- 虫かごの大きさと中に入れる物の選び方
- 飼い方で気をつけたいポイント
- 土の代わりにキッチンペーパーは使える?
ストレスが寿命に与える影響
カブトムシにとってストレスは、寿命を左右する大きな要素のひとつです。快適でない飼育環境が続けば、本来の寿命より早く命を落とす可能性があります。
特に注意したいのは、温度や湿度の変化、過度な振動や音、照明の明るさなど、人間にとっては些細に思える環境の違いです。
これらがカブトムシにとっては大きな負担となり、活動量の減少や食欲不振といった変化につながることがあります。こうした状態が続けば、身体の消耗が進み、結果的に寿命を縮めてしまいます。
例えば、昼夜のリズムが乱れるような明るすぎる場所での飼育は、夜行性であるカブトムシにとっては強いストレスになります。
また、通気性が悪く蒸れやすいケースを使っていると、呼吸がしづらくなり、弱る原因にもなります。
このようなストレスを避けるためには、自然に近い環境を再現することが理想的です。
具体的には、暗く静かな場所にケースを設置し、適度な湿度を保ちつつ、余計な刺激を与えないようにすることが大切です。
ストレスを最小限に抑えることが、カブトムシを長生きさせるための基本です。見た目には元気に見えても、小さな環境の変化が命に関わることもあるため、日々の観察と配慮を忘れないようにしましょう。
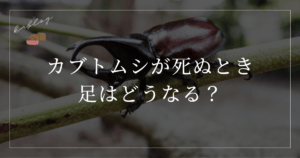
夜にうるさいのはストレスのせい?
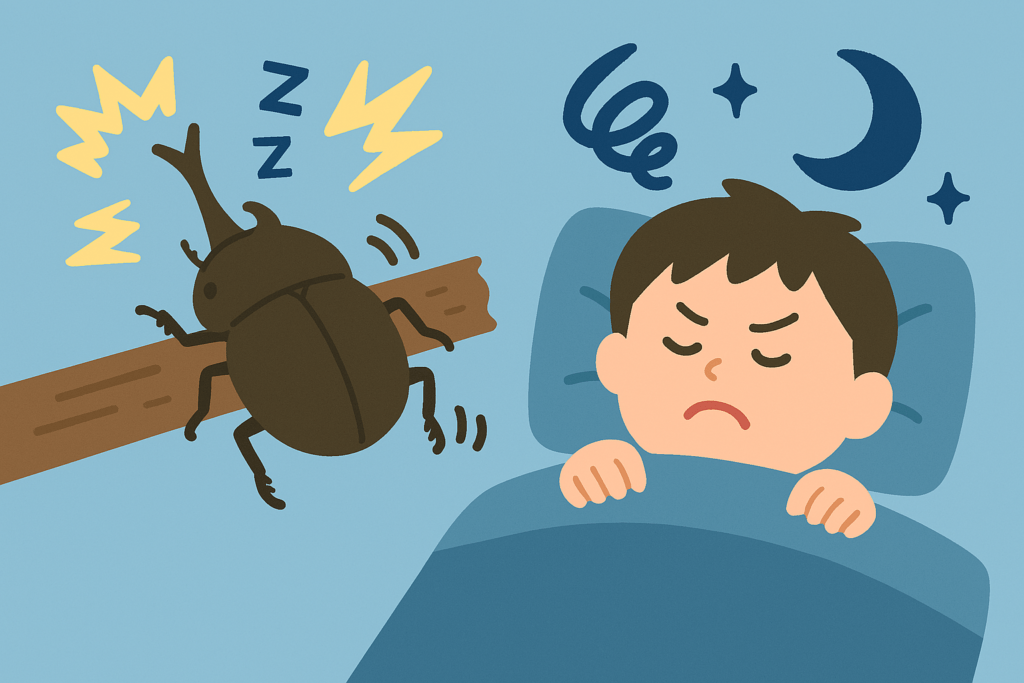
カブトムシが夜にガサガサとうるさく動くのは、ストレスではなく、基本的には習性によるものです。
 ナツ
ナツカブトムシは夜行性の昆虫であり、日が落ちてから活発になるため、夜間に音を立てて動き回るのは自然な行動なんです!
ただし、必要以上に暴れていたり、頻繁に土を掘り返したりするような様子が見られる場合、そこにはストレスが関係している可能性があります。
さらに、気温が高すぎたり、照明が消えずに明るすぎるといった環境の乱れも影響します。カブトムシにとって、暗くて静かな空間が夜の休息に必要不可欠なのです。
夜間の行動が普段よりも激しいと感じたときは、まずは飼育環境を見直してみましょう。ストレスが原因であれば、適切な対応を取ることで落ち着きを取り戻すこともあります。
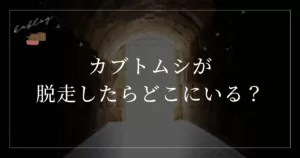
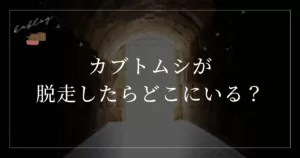
虫かごの大きさと中に入れる物の選び方
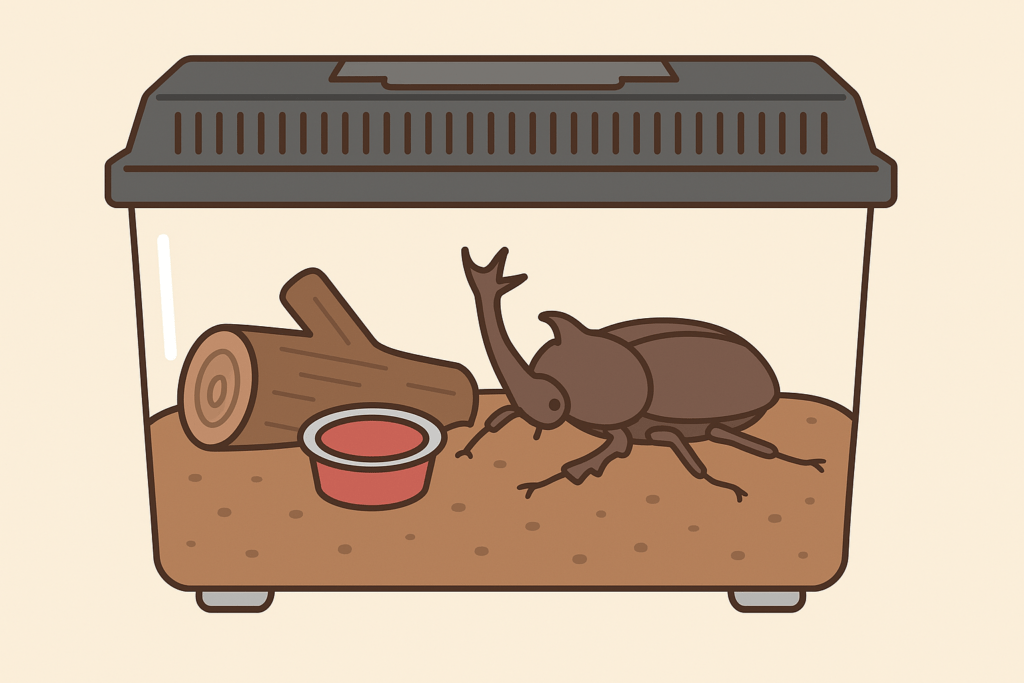
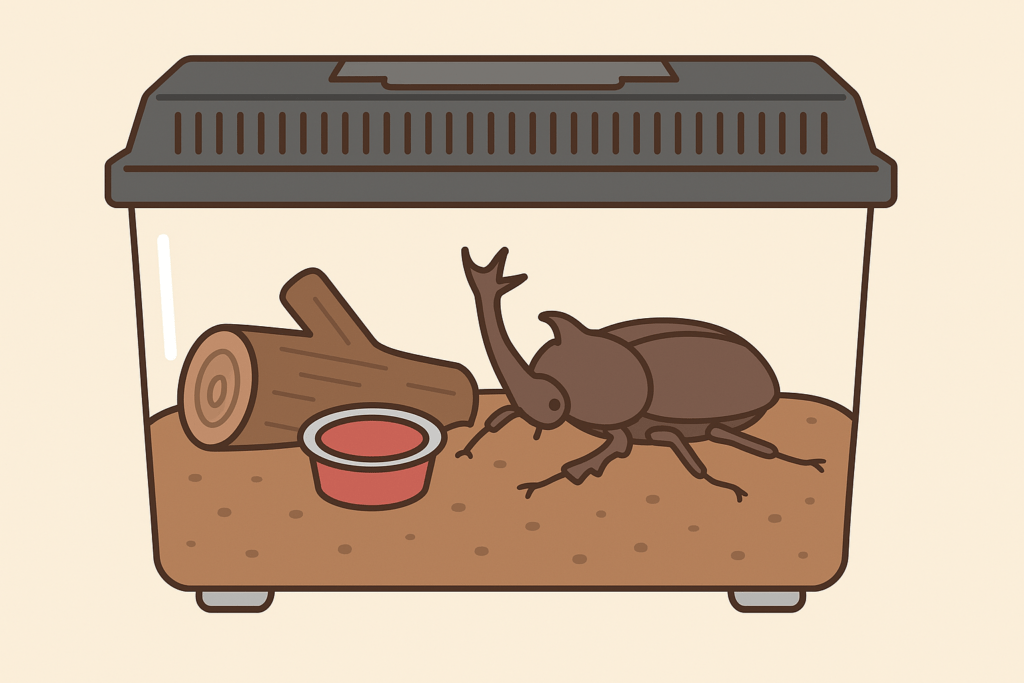
カブトムシにとって、虫かごの広さや中に入れる物は、快適に過ごせるかどうかを左右する大事なポイントです。適切なサイズと配置ができていないと、ストレスにつながるおそれがあります。
まず、虫かごの大きさについてですが、1匹で飼う場合でも、最低でも幅30cm以上のケースが理想的です。複数飼育する場合は、さらに大きなサイズを選ぶことで、縄張り争いを避けやすくなります。狭すぎる空間では、動きが制限され、ストレスの原因になるからです。



単独飼育(個別管理)が長生きのポイントにもなります。
中に入れる物としては、まず床材の選定が重要になります。
腐葉土や昆虫用マットを敷くのが一般的ですが、乾燥を防ぐために適度な湿り気を保ちましょう。また、カブトムシがしっかりと登れる木の枝やエサ皿も必要です。登る行動を取ること自体がストレス解消につながるためです。
逆に、石や硬いプラスチック素材など、足場にならないものは避けた方が良いでしょう。滑って転倒したり、角を傷つけるリスクがあります。
環境を整えてあげることで、カブトムシは安心して生活でき、健康的な成長が期待できます。
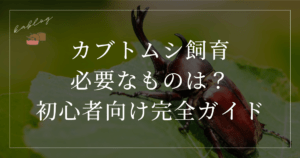
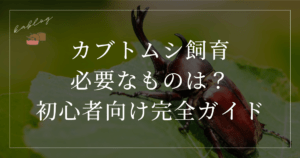
飼い方で気をつけたいポイント


カブトムシを飼う際に気をつけるべき点はいくつかありますが、その中でも環境管理と日々の観察は特に重要です。
まず、温度と湿度の管理が基本です。
カブトムシは高温多湿な環境を好むため、夏場でも直射日光を避け、室温が25〜28℃程度を保てる場所で飼育するのが理想です。
床材が乾燥しすぎると、潜れずに落ち着かなくなってしまうため、時々霧吹きなどで湿らせることも必要です。
次に注意したいのが、エサの与え方です。
ゼリーなどのエサはこまめに交換し、腐敗しないように気をつけましょう。カブトムシは嗅覚が鋭いため、異臭がする環境ではストレスを感じることがあります。
他にも、昼夜のリズムを守るために照明の管理も大切です。人間の生活リズムと異なるため、夜間はしっかりと暗くしてあげることが必要です。
最後に、毎日の観察を忘れないこと。小さな変化に気づけるかどうかが、健康管理のカギになります。動きが鈍くなったり、食べ残しが増えた場合には、何か異変が起きている可能性があります。
正しい知識と心配りがあれば、カブトムシも元気に過ごせる環境をつくることができます。
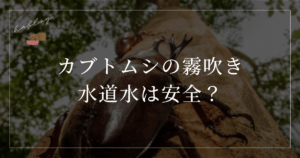
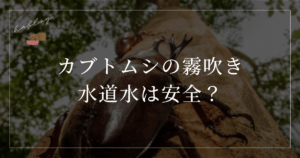
土の代わりにキッチンペーパーは使える?
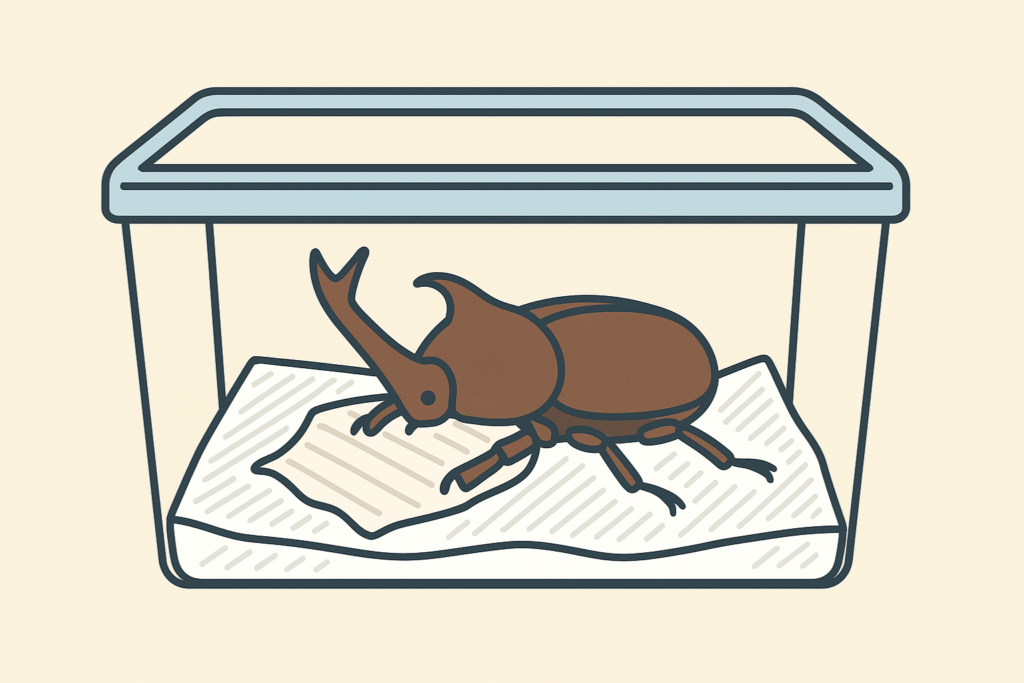
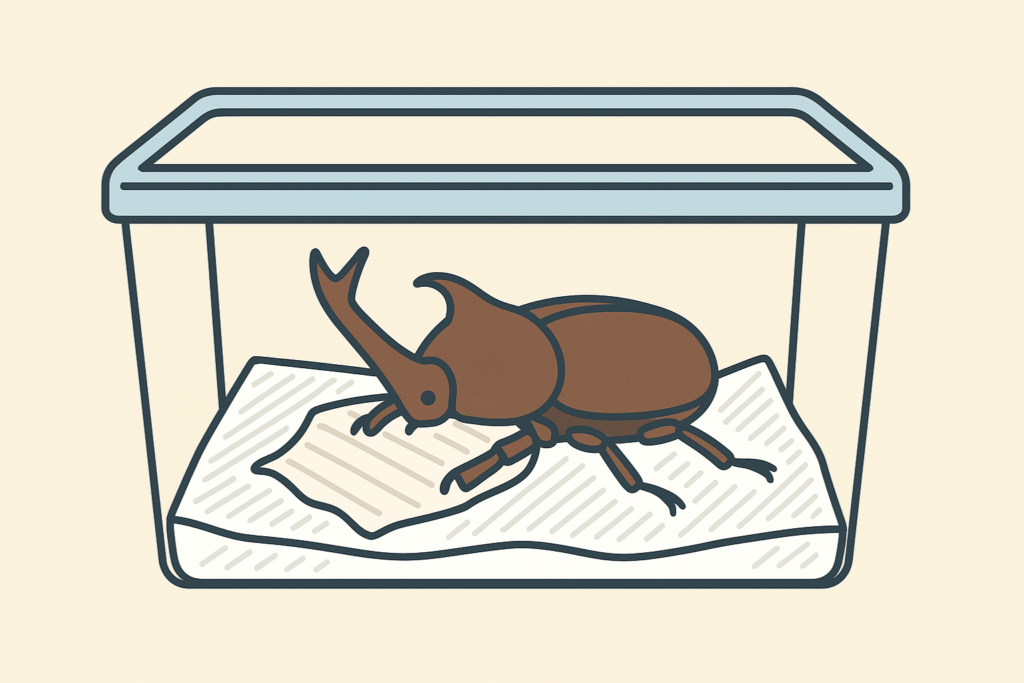
キッチンペーパーを土の代用として使用することは可能ですが、カブトムシの健康を考えると長期的な使用には向いていません。あくまで一時的な代替手段として利用するのが適しています。
キッチンペーパーを使うメリットとしては、掃除がしやすく衛生的である点が挙げられます。幼虫ではなく成虫を一時的に保管する場面や、羽化直後の観察、病気の個体を隔離する際などに有効です。
特に病気やカビのリスクを避けたいときには、清潔さを保ちやすいキッチンペーパーが役立ちます。
ただし、キッチンペーパーではカブトムシが本来持つ「潜る」「隠れる」といった本能的な行動を十分にとることができません。その結果、精神的なストレスが蓄積し、食欲不振や活動の低下につながることがあります。
そのため、日常的な飼育には、やはり腐葉土や昆虫マットなどの自然に近い素材を使用することをおすすめします。
特に繁殖を考えている場合や、長期間の飼育を前提とする場合には、自然素材の方がカブトムシにとってははるかに良い環境となるでしょう。
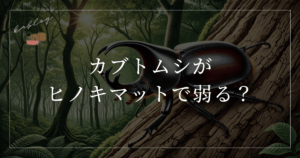
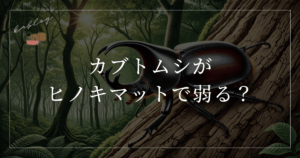
カブトムシのストレスと異常行動の関係
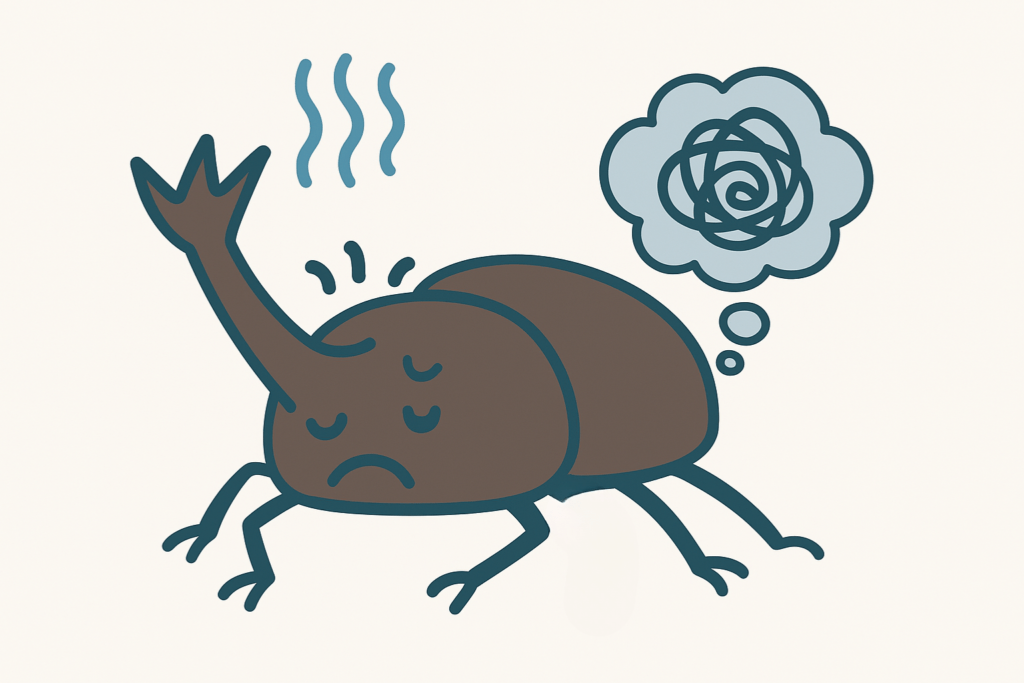
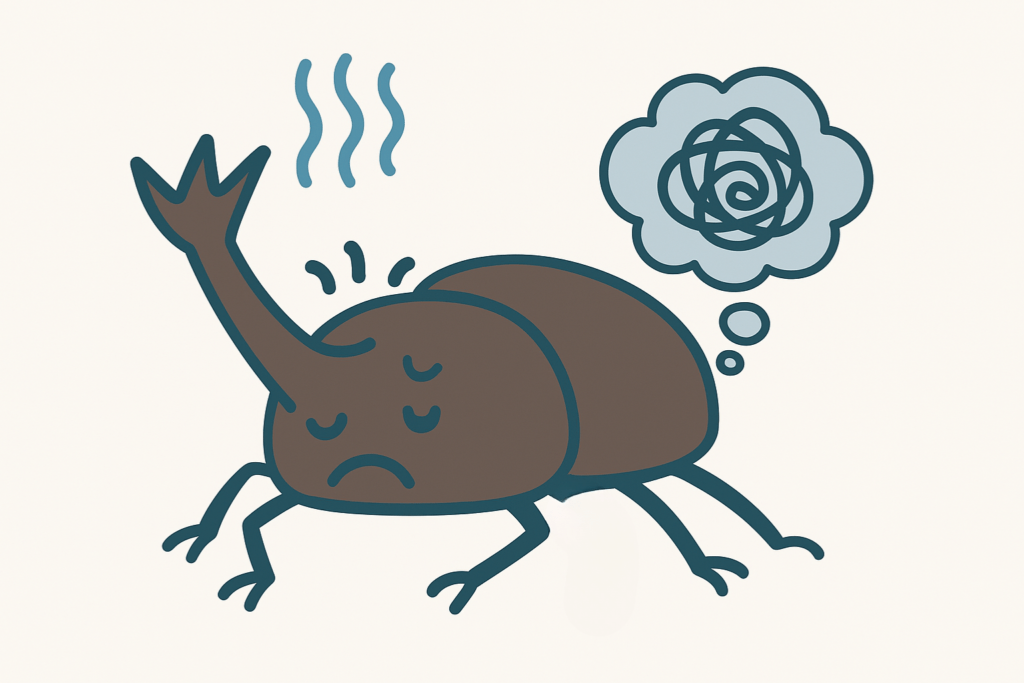
- 死ぬときバラバラになるのはなぜ?
- 死の前兆として見られるサイン
- 動かない・じっとしているときの注意点
- ストレスを減らす環境づくりのコツ
死ぬときバラバラになるのはなぜ?
カブトムシが死ぬときに体がバラバラになっているように見えるのは、自然な現象である場合が多いです。これは病気や外的要因ではなく、死後に関節が緩むことによって起こるものです。
カブトムシの体は硬い外骨格で覆われていますが、脚や羽、頭部などは細かい関節でつながっています。死後しばらく経つと、それらの接合部分が乾燥し、緩みやすくなるため、少しの衝撃や他の個体との接触でパーツが外れてしまうことがあります。
また、飼育ケース内に別の元気なカブトムシがいる場合、死んだ個体にぶつかることでさらにバラバラになるケースもあります。この状態を見て「攻撃されたのでは」と驚く飼い主も少なくありませんが、基本的には自然分解の一環であり、異常ではありません。
もちろん、死ぬ直前に他の個体と争っていた場合や、ケガを負っていた場合は、その影響も加わって体の損傷が激しくなることもあります。そのため、日頃から複数飼育の場合は、十分なスペースを確保し、個体同士のストレスを減らす工夫も必要です。
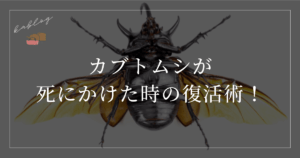
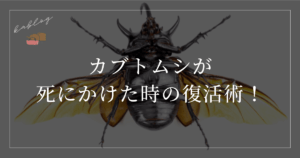
死の前兆として見られるサイン
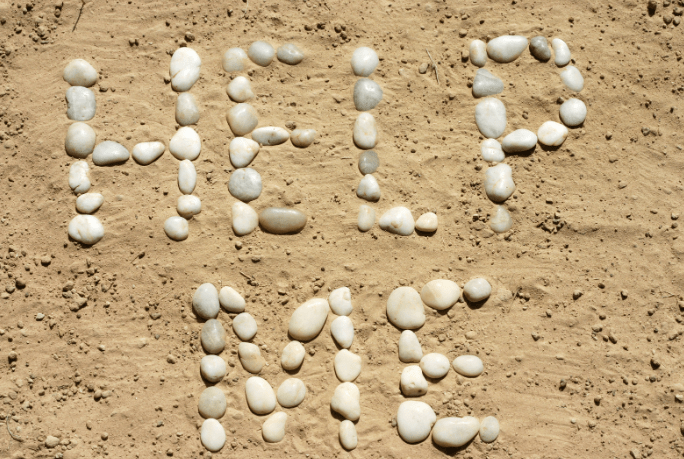
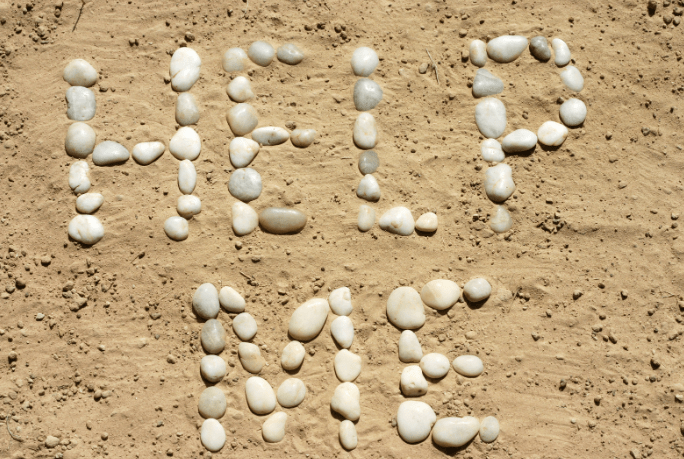
カブトムシが寿命を迎える前には、いくつかの明確な変化が見られます。こうしたサインを早めに察知することで、静かに最期を迎えさせるための準備ができます。
まず、もっとも目立つ変化は「動きが鈍くなる」ことです。これまで元気に動いていた個体が急にじっとして動かなくなったり、壁をよじ登らなくなったりする場合、体力の低下が進んでいると考えられます。
次に、「食欲がなくなる」「ゼリーをほとんど舐めない」といった行動も要注意です。栄養を取らなくなると、内臓の働きが弱まり、寿命の終わりが近づいているサインと考えられます。
さらに、体の色にも変化が見られることがあります。元気なときには光沢がある体表も、老化が進むとツヤがなくなり、くすんだ印象に変わります。また、足の力が弱くなり、うまく立てずに横倒しになったまま動かないケースも多く見られます。



寿命が近くなると符節(足の爪の部分)が取れることもあります。
このような変化が現れた場合は、無理に動かしたりせず、静かな場所で穏やかに過ごせる環境を整えてあげることが大切です。最期までストレスの少ない環境を提供することが、飼い主としてのやさしさにもつながります。
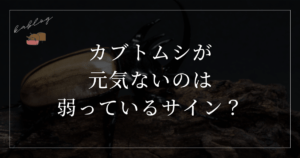
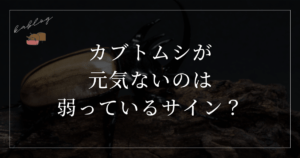
動かない・じっとしているときの注意点
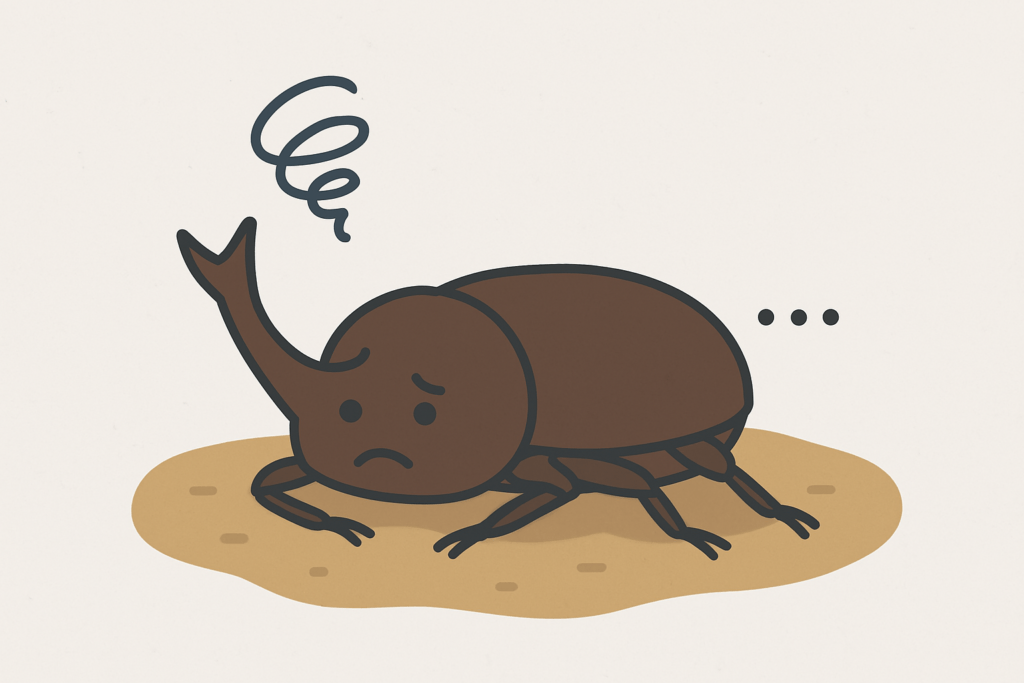
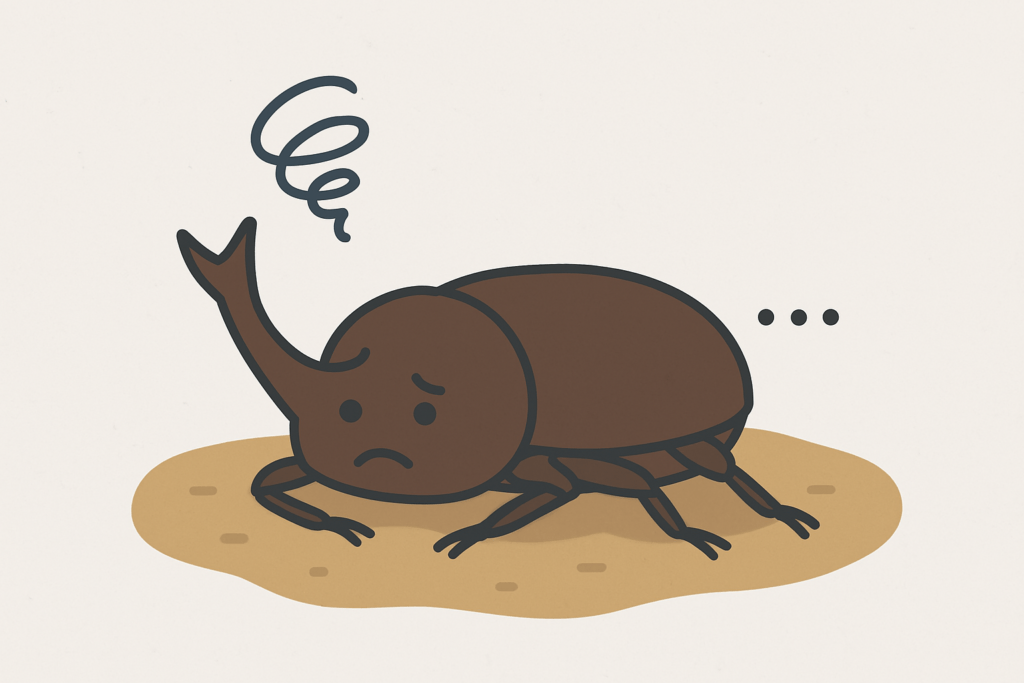
カブトムシがじっとして動かないとき、必ずしも病気や寿命が近いとは限りません。しかし、放置すると命に関わるケースもあるため、状況を冷静に見極めることが大切です。
まず確認すべきは「時間帯」です。
カブトムシは夜行性であり、昼間はほとんど動かず休んでいることが一般的です。昼にじっとしているのは自然な行動なので、無理に触ったり起こしたりする必要はありません。
一方、夜になってもまったく動かない場合には注意が必要です。
このときは、気温・湿度・餌の有無など、飼育環境をすぐにチェックしましょう。例えば、気温が低すぎると代謝が落ち、活動が鈍くなります。特に夏でもエアコンの冷風が直接当たるような場所では、想像以上に体が冷えている可能性があります。
また、餌が古くなっていたり、ゼリーが乾燥している場合、食べられずに弱っていることもあります。ストレスが原因で動かないこともあり、虫かごの大きさや他の個体との同居状況が関係しているケースもあります。
明らかに反応がない、脚が動かない、仰向けのまま戻れないといった場合は、寿命が近づいているサインの可能性があります。ただし、見た目では判別が難しいことも多いため、急な環境変化を避け、落ち着いて様子を見ることが重要です。
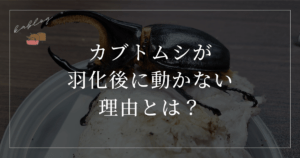
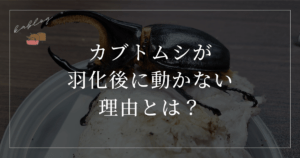
ストレスを減らす環境づくりのコツ


カブトムシの健康を保つためには、ストレスの少ない環境を整えることが基本です。少しの配慮で寿命や行動に大きな違いが出るため、飼育環境の見直しは非常に重要です。
まず、最も大切なのは「静かで安定した場所に虫かごを置くこと」です。
テレビの近くや人の出入りが多い場所は避け、落ち着いて過ごせる場所を選びましょう。音や振動はカブトムシにとって大きなストレスになります。
次に、「飼育ケースの広さ」にも気を配る必要があります。
狭すぎるケースでは身動きが取れず、特に複数飼育の場合は喧嘩や圧迫感によって精神的負担が増します。1匹でもある程度の広さがあるケースを選ぶことが望ましいです。
飼育床には、適度に湿った腐葉土や昆虫マットを使用し、潜ったり休んだりできる環境を整えます。
通気性を確保しながら、乾燥しすぎないように湿度管理をすることも忘れてはいけません。湿度が低すぎると脱水や活動不全の原因になり、高すぎるとカビの発生リスクが高まります。
照明の扱いにも注意が必要です。昼夜のリズムを守るため、常時ライトを点灯させるのではなく、自然な明暗のサイクルを意識することが、カブトムシの体調を整えるポイントになります。
これらの配慮を積み重ねることで、カブトムシが安心して過ごせる環境が整います。ストレスの少ない環境は、健康的な生活と長寿に直結するため、毎日の飼育において最も意識すべき点のひとつです。
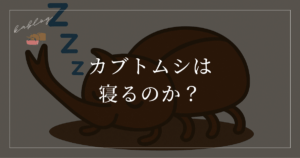
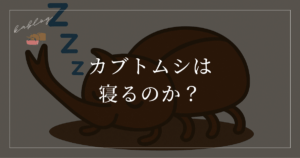
まとめ|カブトムシ ストレスを減らすために大切なこと
記事のポイントをまとめます。
- 飼育環境のストレスが寿命を縮めることがある
- 昼夜のリズムが乱れると体調に影響を与える
- 明るすぎる場所は夜行性のカブトムシに負担になる
- 大きな音や振動が続くと落ち着かなくなる
- 通気性の悪いケースでは呼吸がしづらくなる
- 必要以上に暴れるのはストレスのサインかもしれない
- 夜に動きが活発なのは基本的に自然な行動
- ケースが狭いとストレスやケンカの原因になる
- 滑りやすい足場は転倒やケガにつながることがある
- 床材は湿り気があり清潔なものを使うと安心できる
- エサが傷んでいるとストレスや体調不良につながる
- キッチンペーパーは短期間の代用品としては使える
- 死後に体がバラバラになるのは自然な現象のひとつ
- 食欲がなくなったり動きが鈍くなるのは寿命のサイン
- 静かで暗い場所にケースを置くとストレスが減らせる

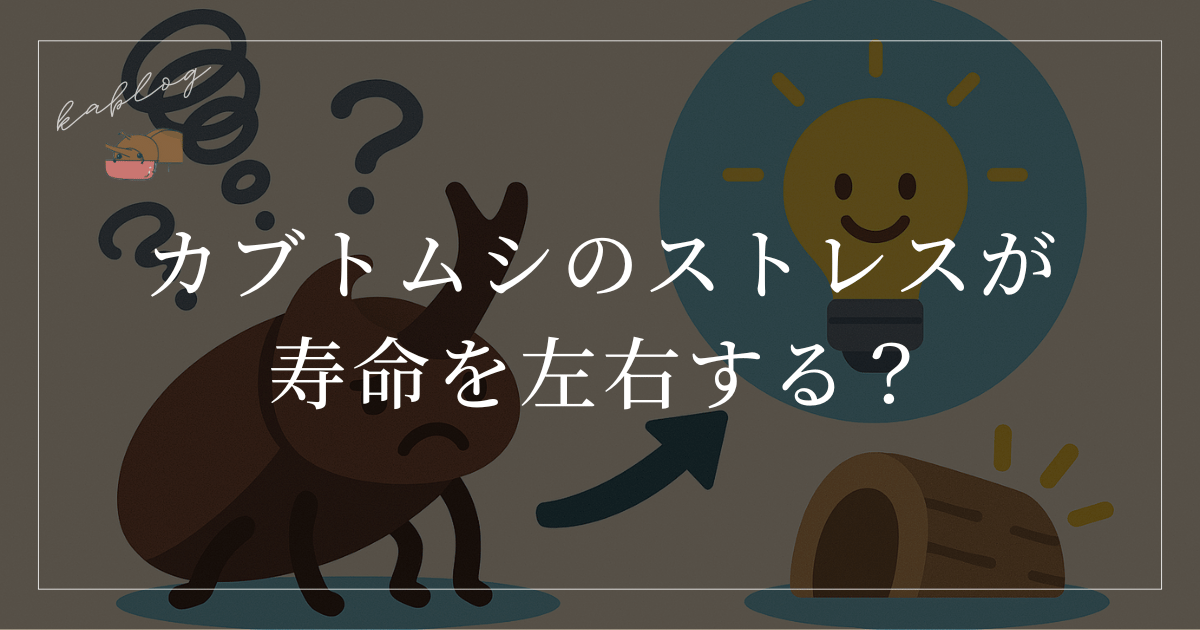
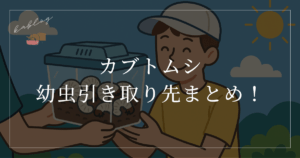
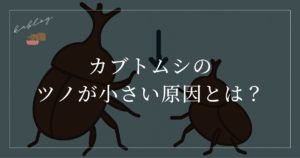
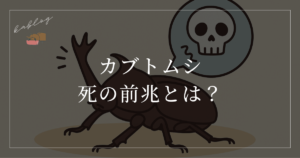
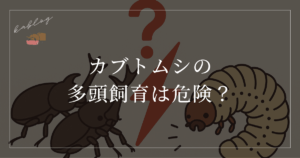
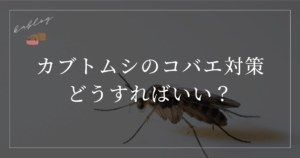
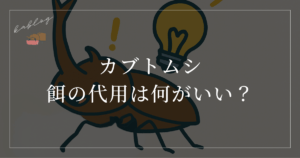
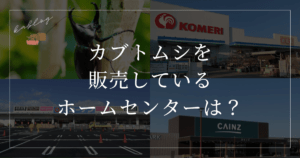
コメント