カブトムシを飼育していると、ある日突然元気がなくなったり、様子がおかしくなったりすることがあります。「カブトムシ 死の前兆」と検索している方の多くは、大切に育ててきた個体の異変に不安を感じているのではないでしょうか。
死ぬ前に暴れる、ひっくり返る、足が動かなくなるといった行動には、寿命が近づいているサインが隠されています。さらに、死ぬときに体がバラバラになるケースもあり、見た目に驚くことも少なくありません。
一方で、死にかけのように見えても復活することもあり、その見極めは簡単ではないのです。
この記事では、成虫や幼虫の段階で見られるさまざまな死亡前の兆候や、死亡率が高くなる時期、注意すべき変化について詳しく解説します。
カブトムシの最期をきちんと理解し、正しい知識で向き合うための参考になれば幸いです。
- 死の前に見られる行動の意味
- 寿命と体調変化の関係
- 幼虫が死にやすい時期
- 死後に体が崩れる理由
この記事を書いてる人
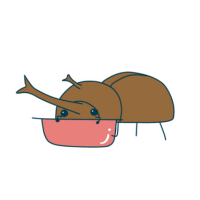
ナツ
- どんな人?
30代フリーランサーで二児の父してます。 - ブリード歴は?
2022年春よりカブトムシ・クワガタのブリード開始。 - どんな種類を飼育してる?
カブトムシはヘラクレスやサタンなど、クワガタはニジイロやメタリフェルなどを主にブリードしており、常時200匹以上飼育中!
カブトムシ死の前兆に見られる兆候

- 死ぬ前に暴れる・動き回る理由
- カブトムシがひっくり返るのはなぜ?
- 死ぬときに足が動かなくなる理由
- 死ぬときに体がバラバラになる原因
死ぬ前に暴れる・動き回る理由
カブトムシが死ぬ直前に暴れたり、活発に動き回ったりする様子を見て驚く人は少なくありません。
これは「最後の力を振り絞る行動」として知られています。
この行動は、体内のエネルギーを使い切ろうとする自然な反応だと考えられています。加齢や寿命によって内臓機能が低下し、体のコントロールが効かなくなると、バランスを崩したり、無意味に動き続けたりするのです。
例えば、健康なときには木にしっかりつかまっていたカブトムシが、死期が近づくと急に木から落ちたり、意味もなく地面を動き回るようになります。これも身体機能の限界によるものです。
このような行動を目にすると「苦しんでいるのでは」と感じるかもしれませんが、実際は生命活動の最終段階で起こる自然な現象であり、特別に苦痛を伴っているわけではないとされています。あくまで穏やかに見守る姿勢が求められます。
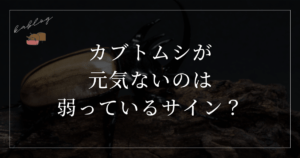
カブトムシがひっくり返るのはなぜ?
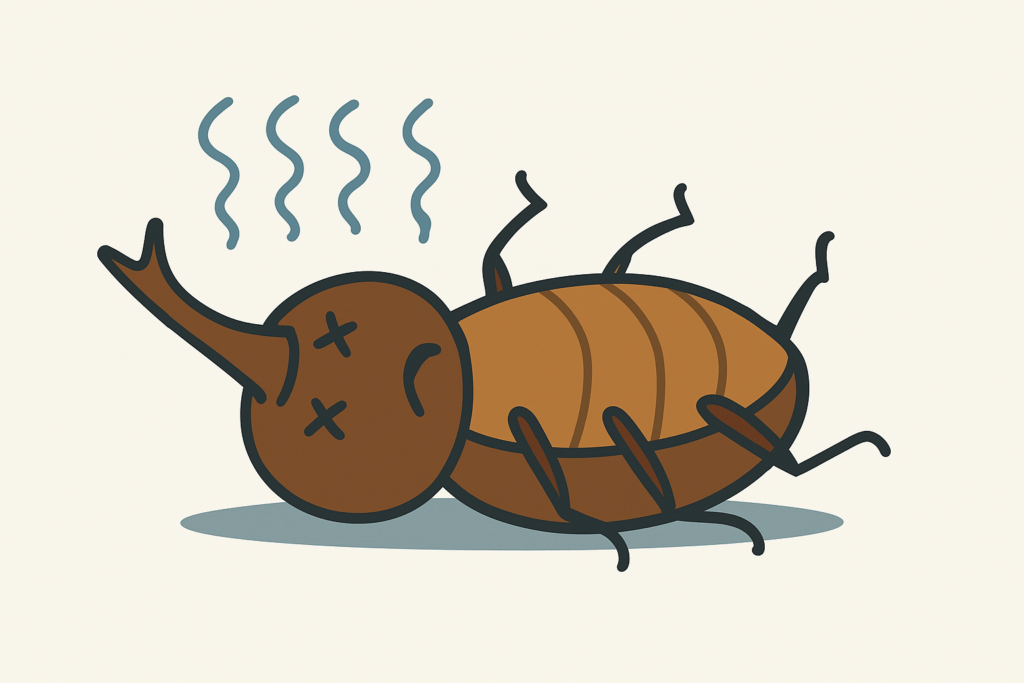
カブトムシがひっくり返って起き上がれなくなるのは、寿命が近づいているサインのひとつです。この現象は、体力や筋力の低下によって起こります。
本来、カブトムシは脚力が非常に強く、多少の段差や傾きがあっても自力で姿勢を立て直すことができます。しかし、寿命が近づくと足の力が弱まり、体を支えたり持ち上げたりすることが難しくなります。
その結果、仰向けの状態から戻れず、じたばたと動くだけで終わってしまうのです。
また、年老いたカブトムシはバランス感覚も鈍くなっており、ちょっとした拍子で簡単に転倒してしまうこともあります。
例えば、エサを食べている最中に体勢を崩したり、容器の壁にぶつかって倒れたりすることがあります。こうしてひっくり返ったままの状態が長く続くと、さらに体力を消耗し、死が早まる原因になることもあります。
 ナツ
ナツひっくり返ると起きあがるのに体力を消耗してしますので、必ず『転倒防止材』を入れてあげましょう!
ただし、若くて元気な個体でも、滑りやすい地面や傾いた環境では転倒することがあります。その場合は、自力で起き上がれることが多いため、すぐに死の前兆とは限りません。
繰り返しますが、問題は「自分で起き上がれない状態が続くかどうか」です。ひっくり返った状態が頻繁に見られるようになった場合は、寿命の終わりが近づいている可能性が高いでしょう。
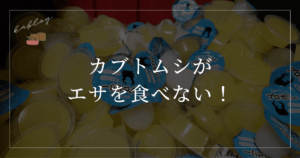
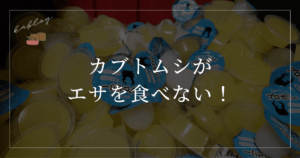
死ぬときに足が動かなくなる理由
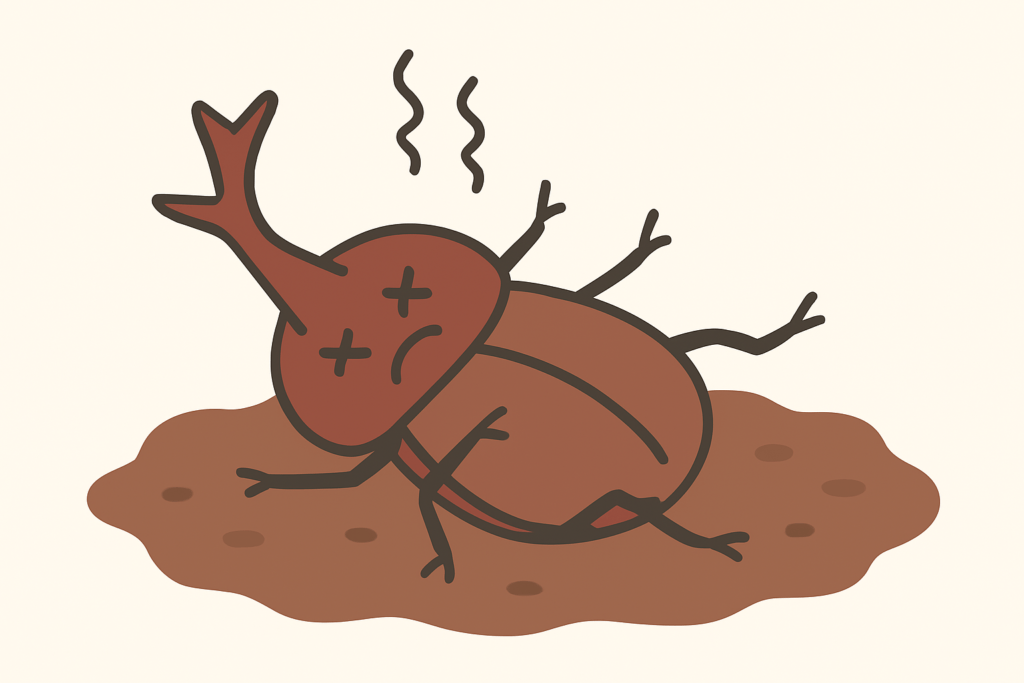
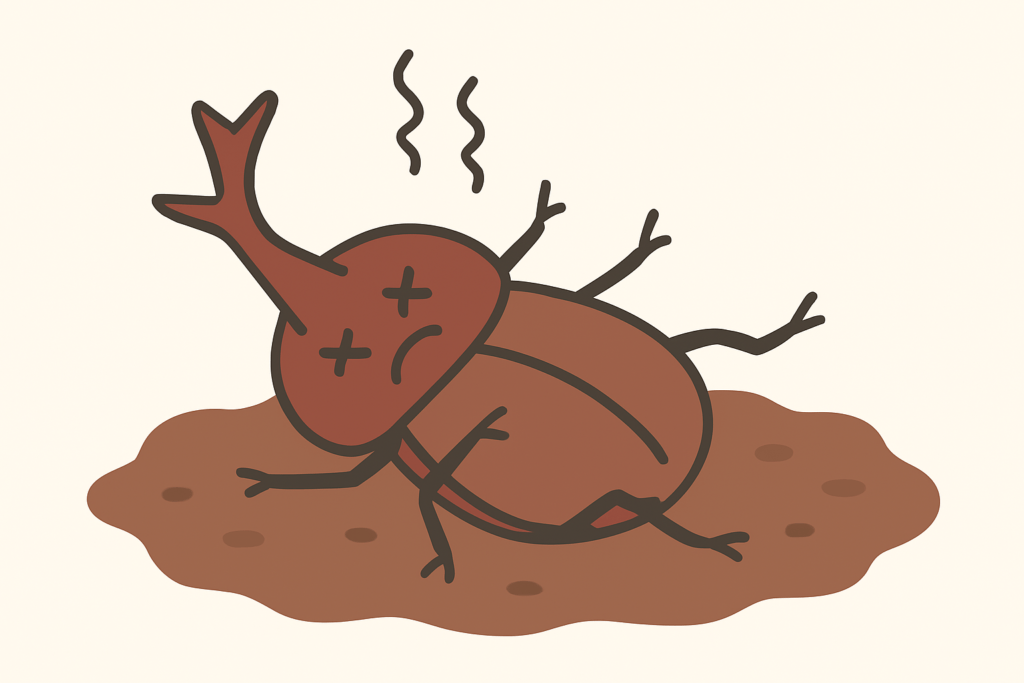
カブトムシが死ぬ間際になると、まず目に見えて変化するのが「足の動き」です。特に、しっかり木やエサにしがみつく力がなくなり、だらんと力なく足を伸ばすようになります。
この原因は、筋肉や神経の老化によるものです。人間と同じく、昆虫も加齢により身体機能が徐々に低下していきます。足の関節が硬直したり、動かしづらくなったりすることで、行動全体に影響が出るのです。
これを放置すると、カブトムシは立ち上がることすらできず、やがて動かなくなってしまいます。体を支える足が使えなくなることは、昆虫にとって致命的です。
このときの足の様子には2種類あります。
ひとつは力尽きて足を投げ出すように伸ばしたまま動かない状態。
もうひとつは、硬直して曲がったまま固まる状態です。
どちらも「もう動けない」というサインですので、無理に動かそうとせず、静かに見守るのがよいでしょう。
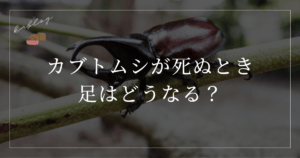
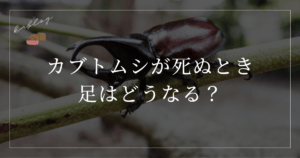
死ぬときに体がバラバラになる原因
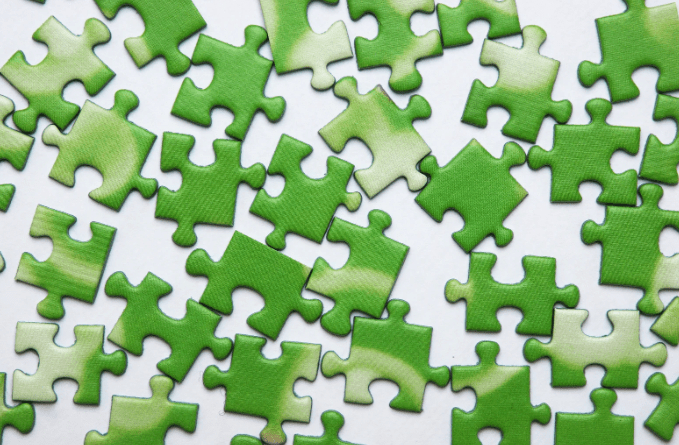
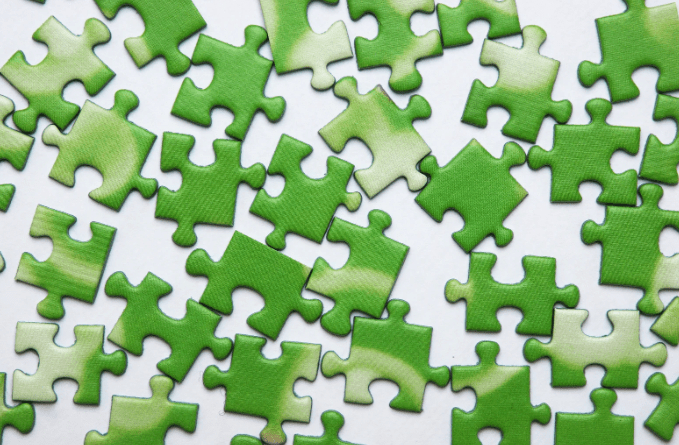
カブトムシの死を迎えるとき、体がバラバラになってしまうことがあります。このような状態になると、まるで外部からの攻撃を受けたかのように見えますが、実際には自然な過程であることも多いのです。
その理由は、死後に筋肉や関節の力が失われ、体の接合部が外れやすくなるためです。特に関節の構造が単純な昆虫にとって、足や羽が取れやすいのは珍しくありません。
また、死後に他の昆虫やダニ、微生物などに分解される過程で、体が崩れることもあります。湿度が高い飼育環境では、この分解が早く進むことが多く、気がついたら体の一部が取れていたということもあります。
さらに、死に際に暴れたことで自分の体を傷つけたり、強くぶつかって部位が脱落したりする場合もあります。これも、寿命や弱り切った状態での動きによるものです。
このように、カブトムシの体がバラバラになるのは必ずしも異常ではなく、寿命や環境の影響、死後の自然な変化によって起こることが多いのです。
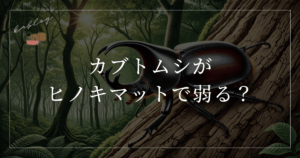
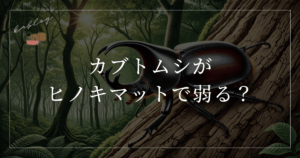
カブトムシ死の前兆と寿命の関係
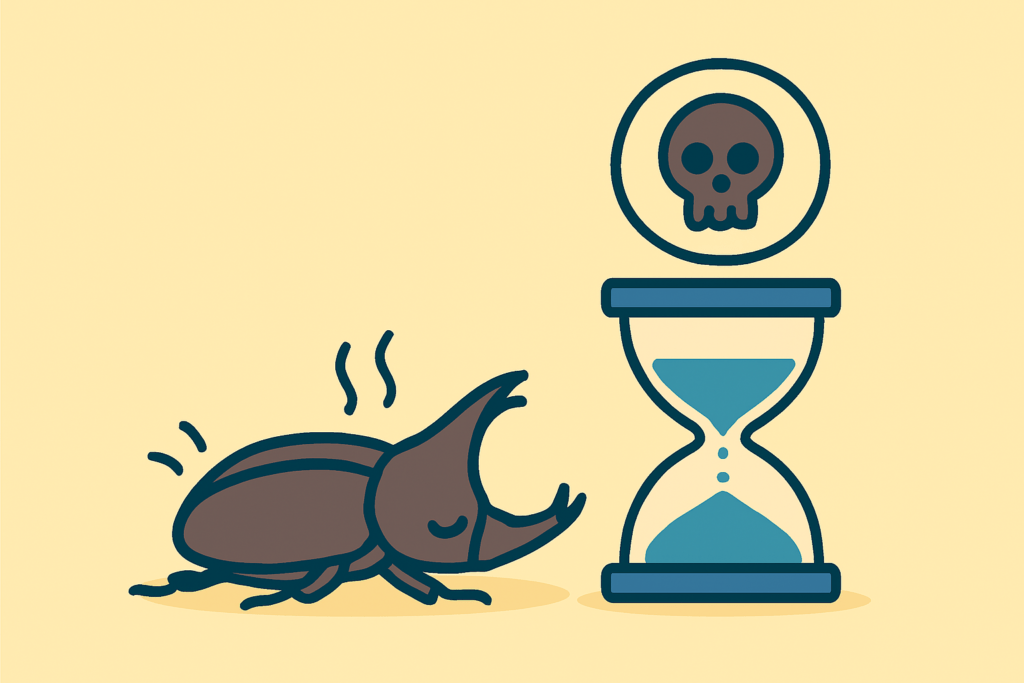
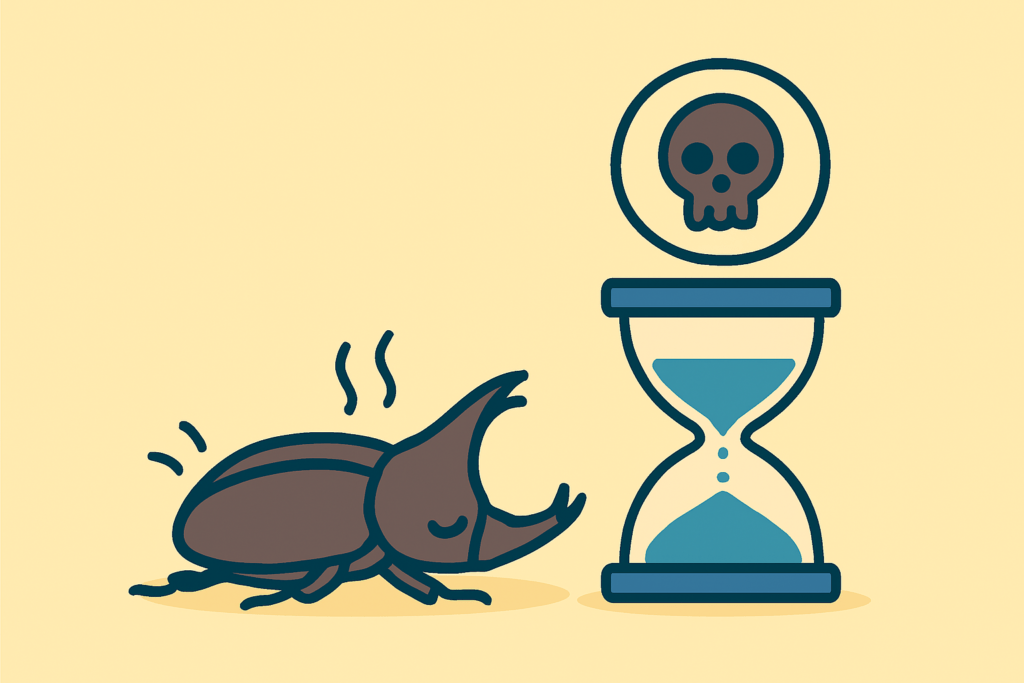
- 成虫の寿命と死の前兆を知る
- 幼虫の死亡率が高くなる時期とは
- 死にかけから復活する可能性は?
成虫の寿命と死の前兆を知る
カブトムシの成虫としての寿命は、一般的に1~3か月ほどとされています。長くても秋まで生きることはまれで、夏の終わりにはその多くが寿命を迎えます。
この寿命が近づくと、カブトムシにはいくつかの前兆が見られるようになります。
まず最もわかりやすいのが、動きが鈍くなる点です。エサに反応しなくなったり、あまり動かずじっとしている時間が長くなったりします。それに伴い、足の力が弱くなり、歩くのが不安定になります。
さらに、羽を広げたまま戻せなくなる、ひっくり返ったまま動けなくなるといった異常行動が見られることもあります。これらはすべて、体力や神経機能の低下を示す兆候です。
一方で、寿命が尽きるまでしっかりと活動し、突然動かなくなるケースもあります。そのため、完全に死の前兆を見抜くことは難しい面もありますが、日頃から動きの変化を観察していれば、ある程度の予測は可能になります。
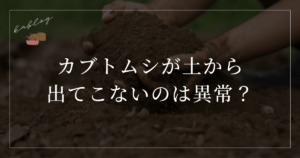
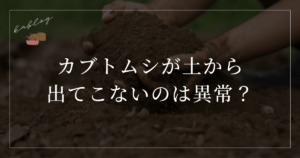
幼虫の死亡率が高くなる時期とは
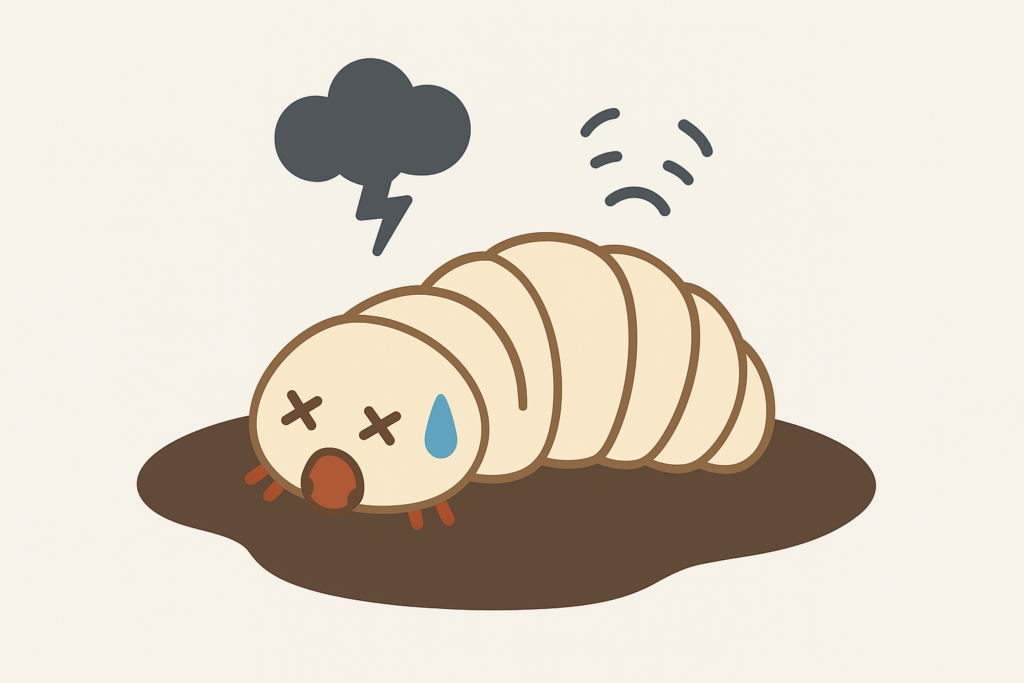
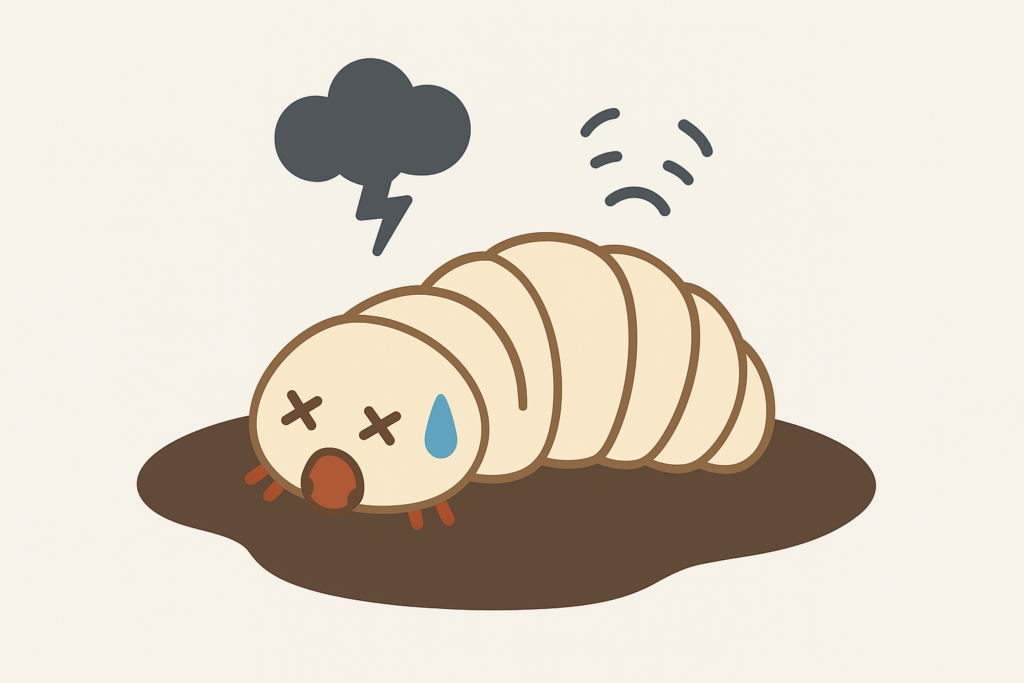
カブトムシの幼虫が最も命を落としやすい時期は、主に「初期の孵化直後」と「蛹化前の成長末期」に集中しています。この時期は環境の影響を強く受けるため、飼育下では特に注意が必要です。
まず、孵化直後の幼虫は体が非常に小さく、乾燥や温度の急変に弱いため、適切な湿度管理がされていないと簡単に死んでしまいます。また、腐敗したマットやカビなどが発生している場合、それを食べて体調を崩すこともあります。



筆者の経験では、孵化直後に亡くなるケースが多いように感じます。
一方、蛹化を控えた終齢幼虫は、栄養不足やストレスによってうまく蛹になれないリスクがあります。たとえば、マットの深さが足りなかったり、周囲から振動が加わったりすると、蛹室をつくれずに命を落とすこともあります。
このように、幼虫の死亡率が高くなる背景には、環境への適応が間に合わないことが大きく関係しています。したがって、飼育する際はマットの状態や温湿度、清潔さを定期的に確認し、安定した環境を保つことが長生きの鍵となります。
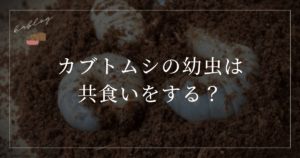
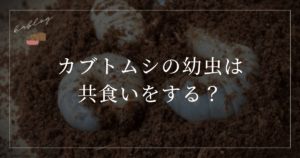
死にかけから復活する可能性は?


カブトムシが弱って動かなくなったとしても、完全に死んでいなければ復活するケースもあります。
例えば、急激な気温の変化や湿度の低下により一時的に仮死状態のようになることがあります。
このような場合は、室温を安定させたり、湿度を調整したりすることで再び動き出すこともあります。特にエサを口元に近づけたときに反応を見せるようであれば、まだ生存している可能性が高いです。
一方で、体が硬直していたり、ひっくり返ったままピクリとも動かない場合は、すでに回復が難しい状態であると考えられます。このとき、無理に刺激を与えたり動かしたりすると、かえって苦しめてしまう恐れがあります。
ここから言えるのは、「死にかけ」と判断したときこそ冷静に対応することが重要である、ということです。完全に死んだと断定する前に、湿度や温度を見直し、少し時間を置いて経過を観察するとよいでしょう。
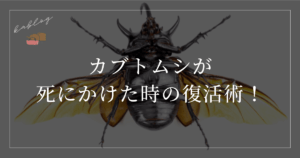
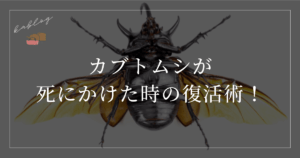
まとめ|カブトムシの死の前兆に関するポイント
記事のポイントをまとめます。
- 寿命が近づくと動きが極端に鈍くなる
- 足の力が弱まり木やエサにしがみつけなくなる
- 死ぬ前に激しく暴れるのは体の制御が効かなくなるため
- ひっくり返って自力で起き上がれなくなることが増える
- 羽を広げたまま閉じられなくなることがある
- 足を伸ばしたまま動かなくなるのは筋力の限界
- 足が硬直して曲がったまま固まる場合もある
- バランス感覚が低下し転倒しやすくなる
- 死後は関節が外れやすく体がバラバラになりやすい
- 飼育環境が悪いと死後の分解が早まりやすい
- 若くても環境によっては一時的にひっくり返ることがある
- 暴れて体の一部を傷つけることが死因につながることもある
- 幼虫期では孵化直後と蛹化前に死亡リスクが高まる
- 仮死状態に見えても環境改善で復活する可能性がある
- 完全に動かなくなる前に前兆を観察することが重要

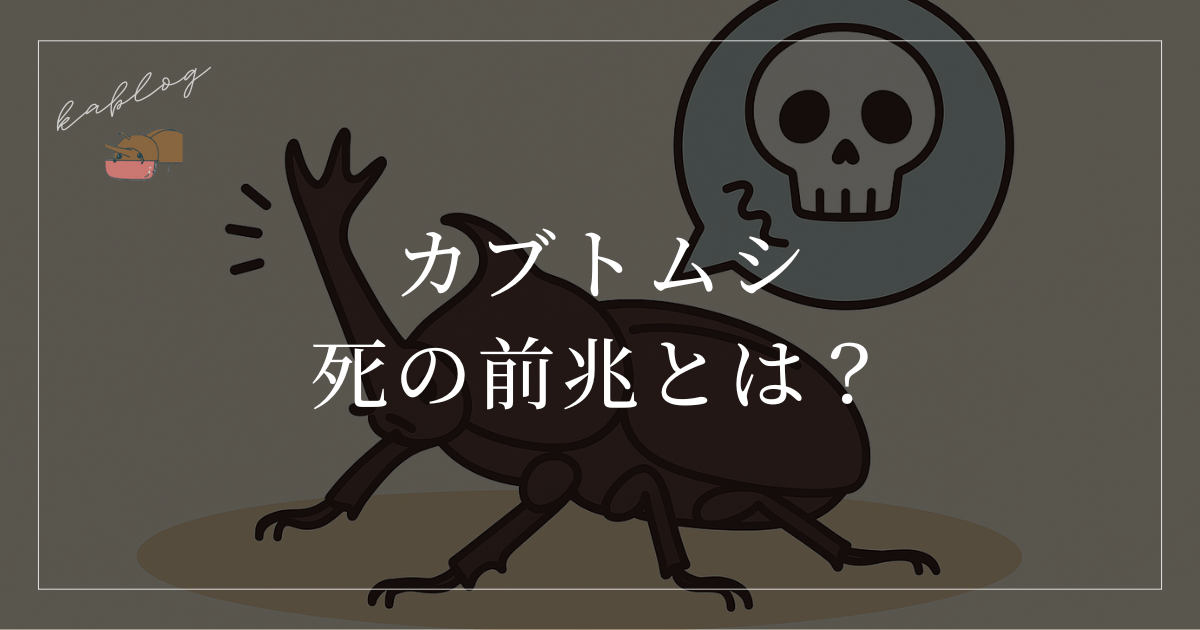
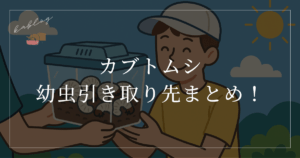
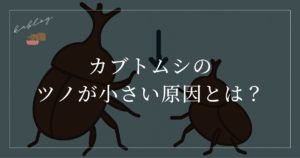
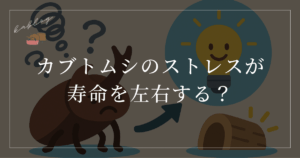
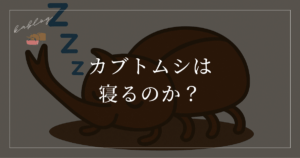
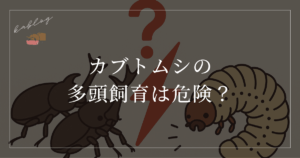
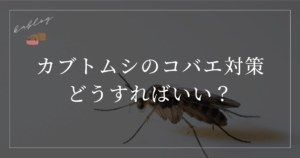
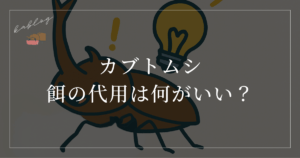
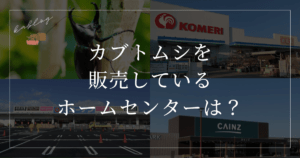
コメント